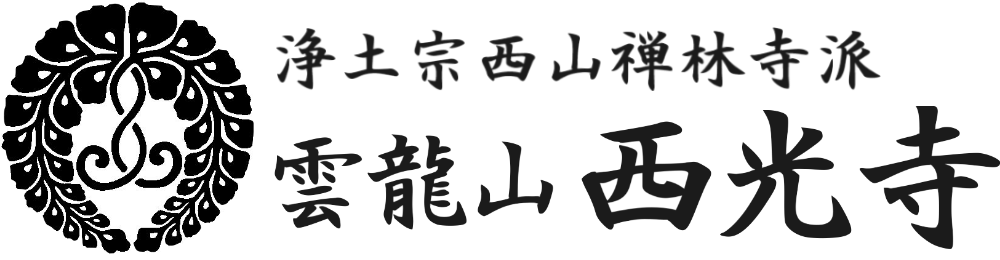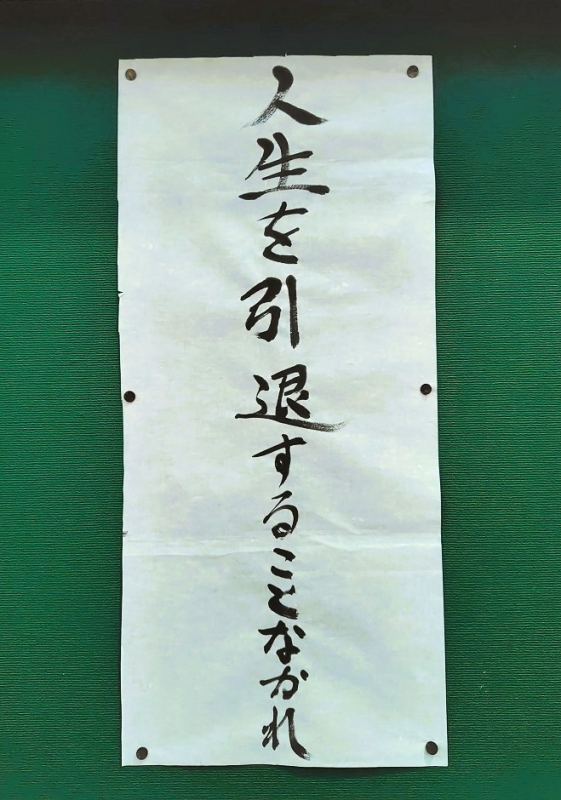人生百歳時代になり、リタイヤ後を余生というにはあまりに長い時間が待ち受けています。余生=余りの人生ではなく、与生=与えられた人生という風に捉えて生きていきたいものです。
最古の経典の一つともいわれる『法句経(ダンマパダ)』の中に「老い」についての言及があります。
白髪の頭になったから長老なのではない
年をかさねただけならば
いたずらに老いたる人といわれる(『ダンマパダ260』
またこうも説かれています。
聞くことの少ない人は、牛のように老いる
かれの肉は増えても、かれの智慧は増えることがない(『ダンマパダ152』)
聞くことは学ぶということです。
お経は亡くなった人への供養のためのものと思いがちですが、お経=仏の教えは、今を生きる人がどのように生きるべきかを説いています。一見現実に生きる私たちの生活に全く関係なさそうな極楽の話や仏の話をお釈迦さまが説くところの意図は、やはり今を生きる私たちの生き方に密接にリンクしているからに他なりません。そういう意味で、この「りょうかん法話」はNo 仏教,No Lifeとしています^^
上のお釈迦さまの言葉の中に「智慧」とあります。知識ではありません。もちろん学びによって知識は増えますが、身に付けるべきは智慧だといいます。智慧は物事の道理を見極め、判断していく心の作用・・・といっても「?」ですね。
私自身僧侶になって思うのは、人に寛容になれたり、人は人と思えたり、そもそも悩まなかったりと、いわゆる自らを苦しめるもの=煩悩から少し距離をとれるようになっていることです。これも智慧です。「仏教を学んで何かいいことあるのですか?」と聞かれれば、この「智慧」が身に付きますというのが答えになります。毎日心穏やかに、今日も良い一日であったと思いつつ寝ることができればいうことはありません。
一生学び、感動し、ときめく日々でありたいですね。遅すぎるということはありません。