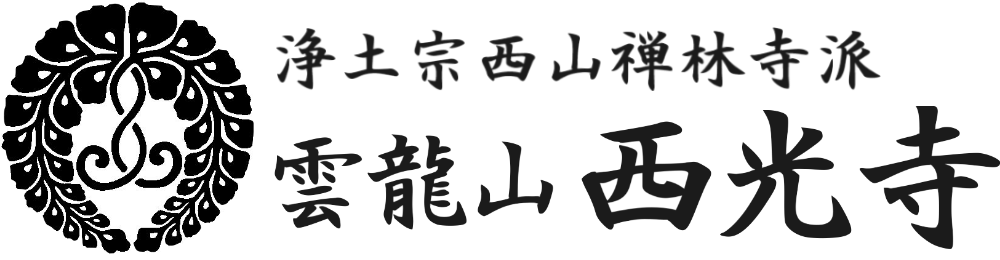善導忌とは、3月14日がご命日の善導大師の忌日法要で、今年で1345年を迎えます。
法然上人は浄土宗を開かれた方としてよく知られていますが、善導大師となると途端に「誰?」となるでしょう。浄土宗のお仏壇では、ご本尊の阿弥陀仏の向かって左側に法然上人がお祀りされ、上座の向かって右側に法然上人が師と仰ぐ善導大師がお祀りされます。師匠といっても国も時代も違うので直接はお会いになっておりません。しかし夢でお会いになっています。法然上人が夢でお会いした時に、善導大師の下半身が金色に輝いていたので、お仏壇の善導大師も体の下半分は金色になっています。
善導大師は中国唐の時代に浄土の教えを大成されました。法然上人は、比叡山の経蔵(比叡山黒谷青龍寺の報恩蔵)に籠り、自らの求める教えはないものかと全ての経典を何度もお読みになられ、ようやく善導大師の『観経疏』に出会い、ここから浄土宗開宗へと繋がってまいります。
我が派の播州地方で行われる善導忌の起源は、江戸時代の元禄5年(1692年)に始まります。この年、京都の本山永観堂にて勤められる善導忌に出仕しようとしていた播州の寺院が、明石川の氾濫により出仕できない事態となり、急遽明石の江井島長楽寺に集まり、善導忌を勤めたことが起源となっています。それより今に至るまで333年に渡り毎年、播州の門中寺院のうち20ヶ寺が輪番で勤めています。
今年は3月29、30日、西光寺からもすぐ近くの高砂市北浜町西浜の西岸寺で勤められました。私は礼文(らいもん)師と説教師のお役を拝命いたしました。私が担当したのは礼文の内、弥陀礼(みだらい)という声明(しょうみょう)で、阿弥陀さまをお招きし、自らの罪を懺悔(さんげ)して、ますますの仏道精進を表明する偈文(げもん)です。礼文師はご尊前に進み出て、礼文を独唱し、その後に参列寺院方が続いて唱えます。低音の静かな旋律から始まり、中音、上音と次第に高揚して阿弥陀さまを讃えます。
お説教では、善導大師の教えのキーワードの一つでもある「凡夫」を軸に、煩悩にまみれた私たちが他の人々と共に幸せにいきていくためにはどうすればよいのかということを1時間お話しさせて頂きました。
西光寺は5年後に善導忌がまわってきます。