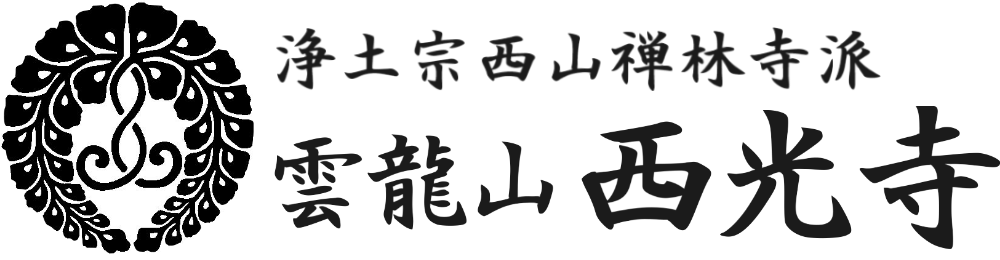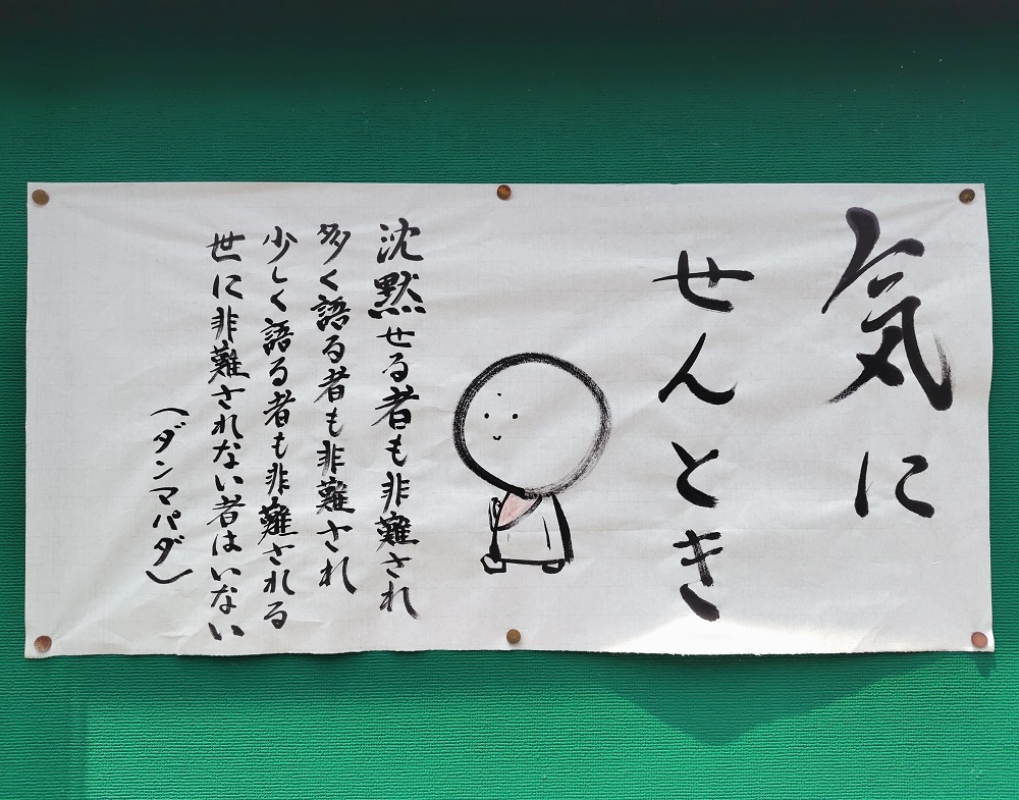昨今、政治家や芸能人などの失言がメディアを賑わせています。今は有名人でなくとも、SNS等を通じて、有ること無いことが拡散されてしまう時代です。「話す」ことが“仕事”の私も他人事とは思えません。同じ言葉でも胸に響く人がいる一方で、傷つけてしまうこともあります。昔はピンとこなかった言葉が、今改めて聞くと、このことば、このエピソードに出会えてよかったと思うこともあります。
沈黙せる者も非難され
多くを語る者も非難され
少しく語る者も非難される
世に非難されない者はいない
これはお釈迦さま自身が一番分かっていたことなのです。非難された時の対処法を示したエピソードがあります。
ある時、多くの人々から尊敬を集めているお釈迦様のことを妬ましく思う男が、「あのいけ好かないアイツに皆の前で悪口を浴びせてやろう。そうしたらムキになって汚い言葉で言い返してくるに違いない。そうすれば、皆から失望されてアイツの人気もガタ落ちだ、ヒヒヒ」と企みました。
ところが、男の意に反して、お釈迦様は腹を立てるどころか、心静かに黙って聞いておられるだけでした。弟子たちが心配になって「あんなひどい事を言わせておいてよいのですか」と言っても黙ったままです。その内に男は張り合いがないものですから、空しくなって座り込んでしまいました。
お釈迦様は、その男にこうおっしゃいました。「他人に贈り物をしようとして、その相手が受け取らなかった時、その贈り物は一体誰のものであろうか」その男は、「相手が受け取らなかったんだから、贈ろうとした者のものだ。そんな分かりきったことをわざわざ聞くな!」と答えたその瞬間、ハッと気が付いたのです。
続けてお釈迦様は、こうおっしゃいました。「その通り。今、あなたは私のことをひどく罵りました。でも、私はその罵りを少しも受け取らなかった。だから、あなたが言った言葉はすべて、あなた自身が受け取ることになるのですよ」