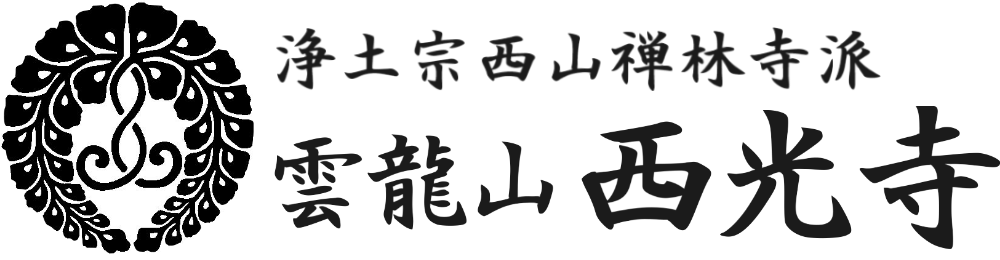施餓鬼。餓鬼に施すと書いて、セガキと読みます。なにやら不気味な感じがしますが、一体何のためにする行事なのでしょうか。
お釈迦様の弟子に阿難(あなん)という方がいました。阿難はお釈迦様の十大弟子の一人で、常にお釈迦様の傍に仕え、もっともお釈迦様の説法を聞いていた人物です。その阿難が修行中、餓鬼が現れ「おまえは三日後に命が尽き、餓鬼に生まれ変わるのだ」と宣告されます。びっくりした阿難は、「助かる方法はないのか」と餓鬼に尋ねると、餓鬼は「救われたければ、無数の餓鬼に飲食を施せ」というのです。
無数の餓鬼に飲食を施せといっても、そのやり方が分からない阿難は、お釈迦様に教えを請います。するとお釈迦様は「施餓鬼棚を設け、海のもの山のものを供えて、多くの僧に供養してもらいなさい。そうすれば、無数の餓鬼に飲食を施すことができる」と説かれました。この少量の食べ物を無量の食べ物に変えるとされるお経が、陀羅尼(だらに)というもので、お盆参り(棚経)の時にあげさせて頂く一風変わったあのお経です。
そんなこんなで、無数の餓鬼に食べ物を施すことができた阿難は餓鬼の世界に墜ちることなく、寿命を永らえることができたというお話です。ちなみに阿難は当時ではかなり長寿だと思われますが、八十八歳まで生きたそうです。
これに由来した行事が施餓鬼というものです。お盆のシーズンにしないといけないということはないのですが、盆施餓鬼として全国のお寺でお盆の時期によく行われます。当寺でも八月七日(永代)、十六日にこの施餓鬼を行っています。お釈迦様が仰せの通り、施餓鬼棚を設け、海のもの山のものを供えて、多くの僧に供養してもらっております。
この由来からすると施餓鬼は、自身の長生きを願うものですが、今日ではご先祖、無縁の諸霊、一切の生物の供養のために行う法要として定着しております。